私たちの両親はもう70を優に超え80代に差し掛かってきました。
まだまだ元気ではあるものの、介護、老後について考えることもしばしば。
40代に差し掛かると、自分たちの家庭や子どものことに追われながらも、「親のこと」が静かに、しかし確実に現実味を帯びてきます。
「最近、母の物忘れが気になる」
「父が車の運転をやめたがらない」
「実家が遠方で、何かあってもすぐに行けない」
こんな不安や戸惑いながらも、これからの両親へのかかわり方について40代夫婦がどう見直し、どう向き合っていくかについて、現実的な視点から考えていきます。
親の“変化”に気づいたときが、話し合いのチャンス
70代を過ぎた親世代に多く見られるのが、健康や体力の衰え、認知機能の低下、判断力のブレなどの変化が起こるのが一般的です。
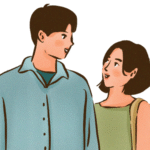
大事には至りませんでしたが、ある日突然の入院や転倒で慌ててしまいました。
いざという時慌てないためにも、両親の変化には気を配っておきたいものです。
- 食事が偏る・痩せてきた
- 家の中が散らかりはじめた
- 通帳やカードの場所をよく忘れる
- 固執した言動や怒りっぽさが目立つ
私の両親は遠方で暮らしているので、定期的な電話や訪問で“今”の様子を知ることを大切にしています。
介護は「いつか」ではなく「備えるもの」
40代は仕事も子育てもまだまだ多忙な時期。そんななかで親の介護が始まると、心身ともに余裕がなくなり、夫婦関係や子どもへの影響も出てきます。
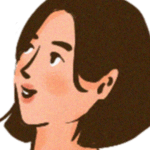
私の10代の頃の話ですが祖父母と同居していたので、祖父母が介護が必要となったときに両親が大変な思いをしていたことを記憶しています。
私は受験を控えてましたが、ゆっくりと進学について話し合うことができずに寂しいかったです。
今となっては、両親が祖父母を大切に介護する姿が近くで見られてよかったと思えますが10代のころはそんな風に思うこともできませんでした。
また、介護はやはり夫婦にとって重くのしかかるものとも感じています。私たちが心配していることについてあげてみました。
介護について不安に思うこと
- 実家が遠方(妻の)で、頻繁に行き来できない
- 兄弟姉妹と役割分担がうまくいかないかもしれない
- 施設を探すタイミングや費用の不安がある
- 親が「まだ大丈夫」と支援を拒むのではなかろうか
こういった不安は、きっとどこのご家庭でもあるのかな?とも思います。
介護の正解は一つではありませんが、早めに「親の希望」「自分たちの限界」「公的支援」などを確認しておくと、慌てずに対応できるのではないでしょうか。
お金の話を避けないで
なかなか切り出しずらいですが、両親が元気なうちにお金の話をすることは必要ではないかと考えています。介護にかかる費用はもちろん、将来的な相続や財産管理など。もし認知症になってしまったらきっと話すこともできないだけでなく、両親の資産は凍結されてしまうかも知れないので、両親の貯蓄で介護費用を賄おうと思っていても、そうできない可能性があるからです。
「お金の話」はセンシティブながら避けて通れないと感じています。
話しておきたいこと
両親が元気なうちに話しておきたいことをまとめてみました。
- 年金額や収入の状況
- 通帳・保険・不動産などの管理方法
- 認知症になったときの資産の扱い(成年後見制度など)
- 介護サービス利用時の支払い能力や意向
話すきっかけとして「家族のライフプランを立てたい」「相続や保険のことを整理したい」など、自分たちの事情を伝えつつ、自然な流れをつくりながら両親に負担がかからないようにゆっくり時間をかけて話していきたいと考えています。
夫婦でできる「親との関係性」の作り直し
親のサポートは、夫婦どちらかに偏るとストレスが溜まりやすくなると思います。
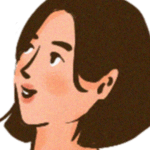
私はパートなので主人より時間があるためどうしても私中心に介護を行うことになるのでは?と思うと不安です。
両親がどのような支援が必要になるかわかりませんが、これからのことを少し話し合っておく必要があると感じました。
- 両家の親に対するスタンス(距離感・支援の範囲)
- どちらかが倒れたときの対応策はどうするか
- 休みの調整、訪問頻度の分担はどう考えているのか
- 両親との感情的なもつれがある場合は、どう緩和するか
無理をしない範囲で「できることをする」ことが大前提。
支援の手は、行政サービスや専門職にも頼ることを前提に考えています。
親との時間も「今」しかない
老いていく親と、ゆっくり過ごせる時間は決して長くないんですよね。とても寂しいですが。
「一緒に旅行に行く」
「昔話を聞く」
「孫と交流する時間をつくる」
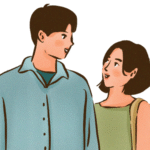
介護の前段階だからこそ、「思い出を作る」ことができるとおもいます。重いテーマだけでなく、温かい交流の時間も意識して持ち両親との時間を大切にしていきたいと考えています。
親との関係性も“柔らかく”再構築を
40代は、親の老いに向き合い始める大切なターニングポイントと改めて感じました。現実を知り、話し合い、必要な備えを始めることで、後悔のないサポートが可能になるのではないでしょうか。
大切なのは、「親をどう支えるか」だけでなく、「夫婦でどう支え合うか」という視点。家族はチーム。だからこそ、話し合いと協力が鍵になります。大切な両親との時間をより充実した時間にするために寄り添いながらゆっくりと話し合っていきたいと思います。
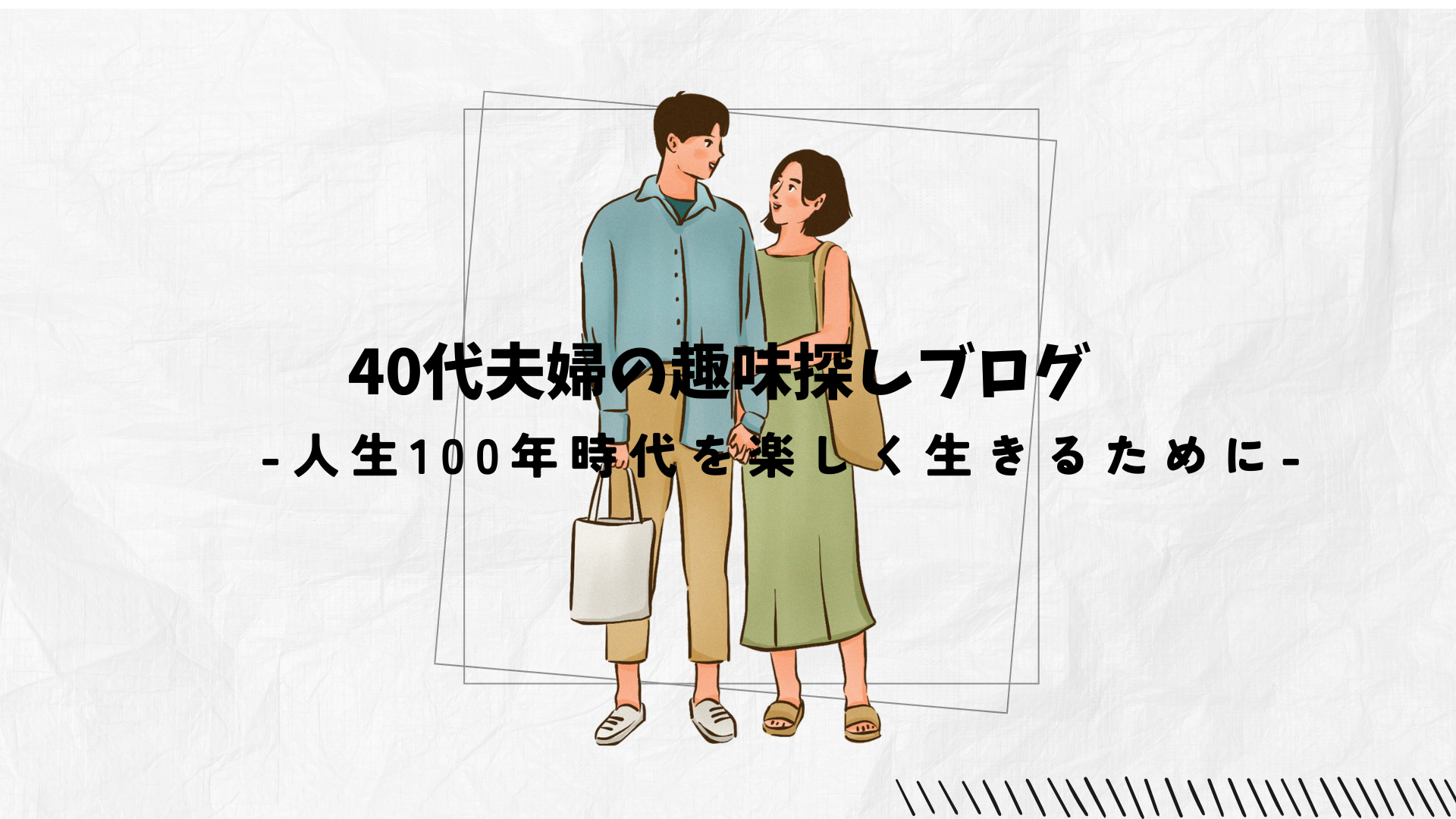
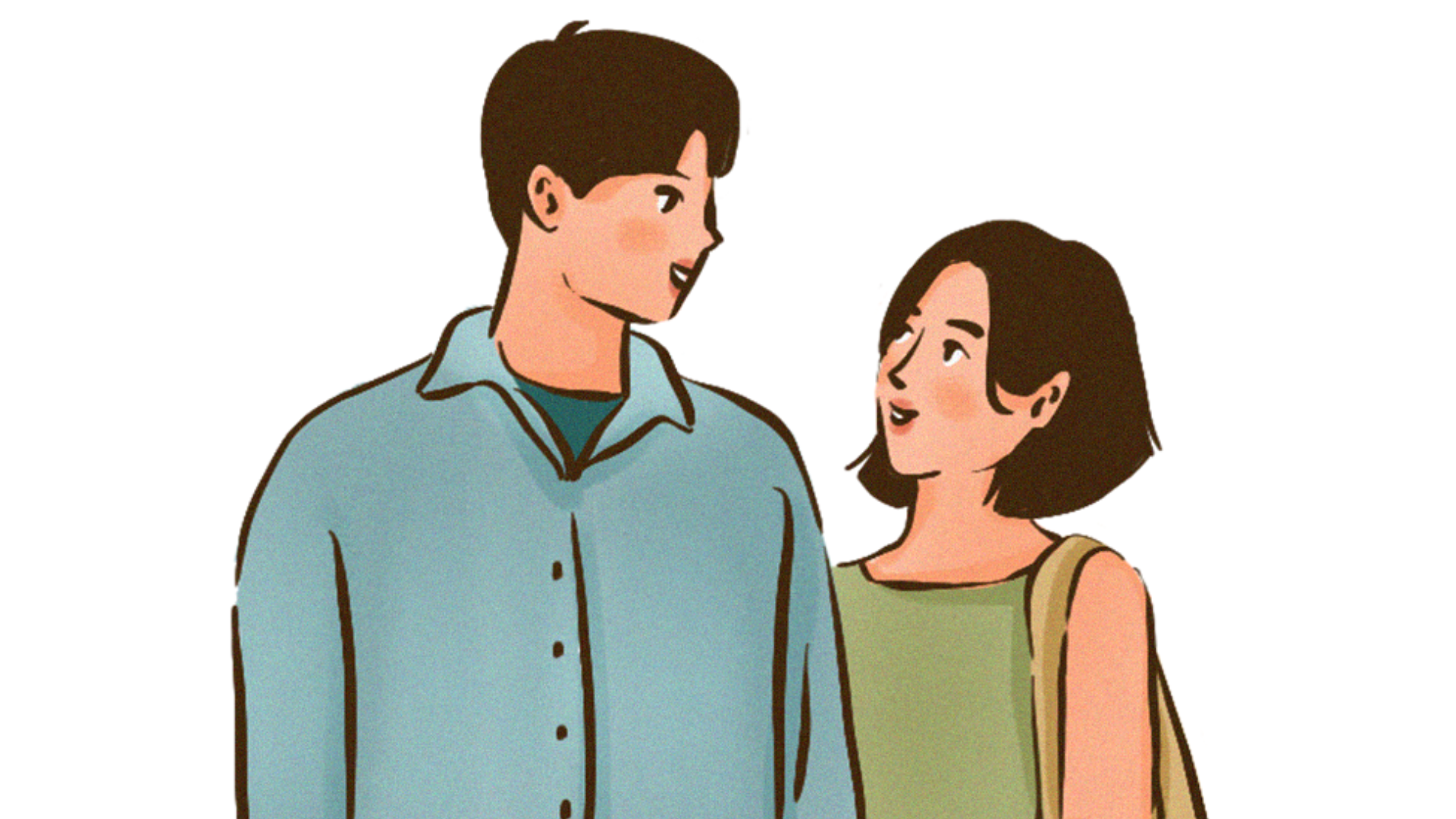
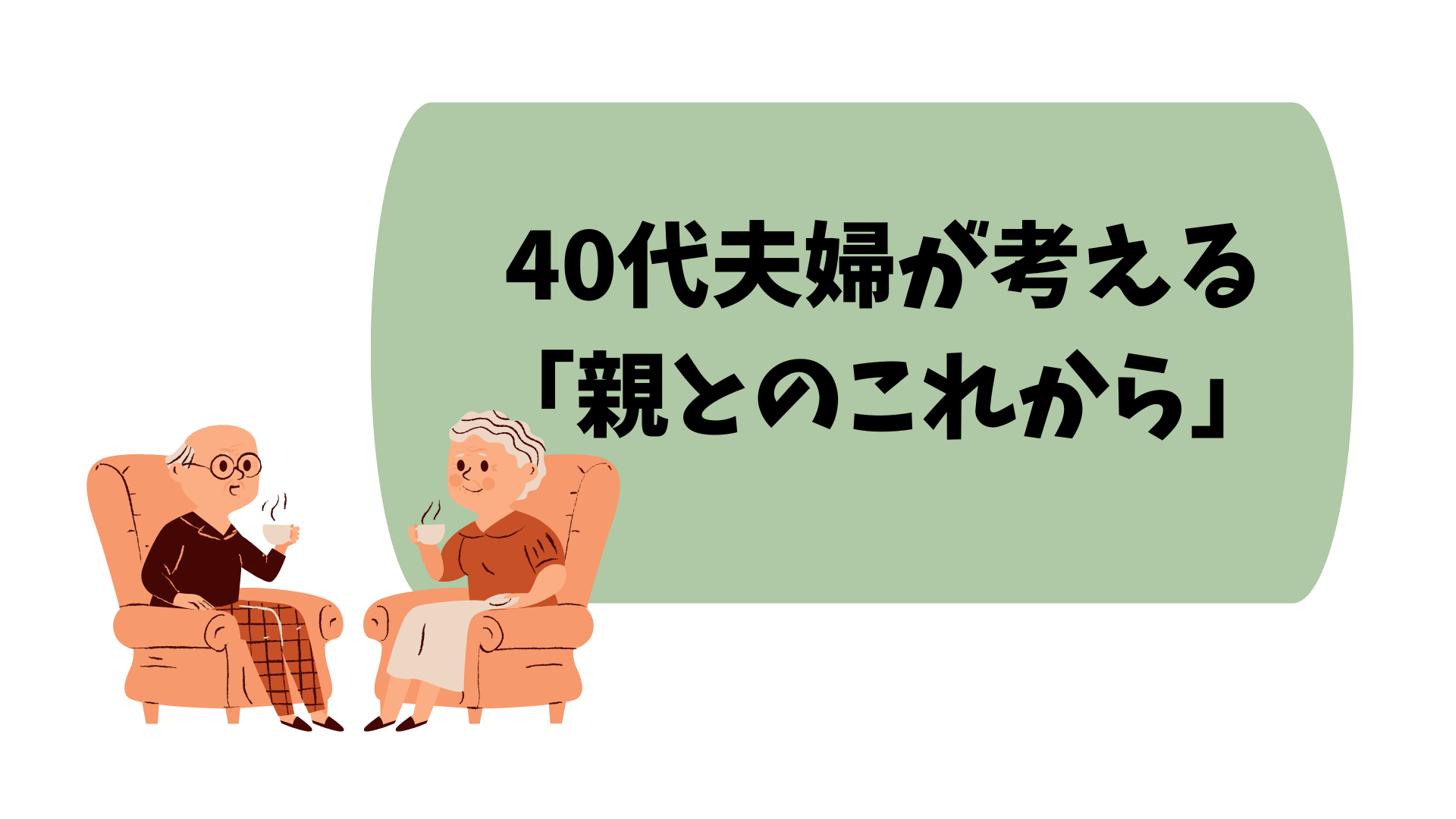
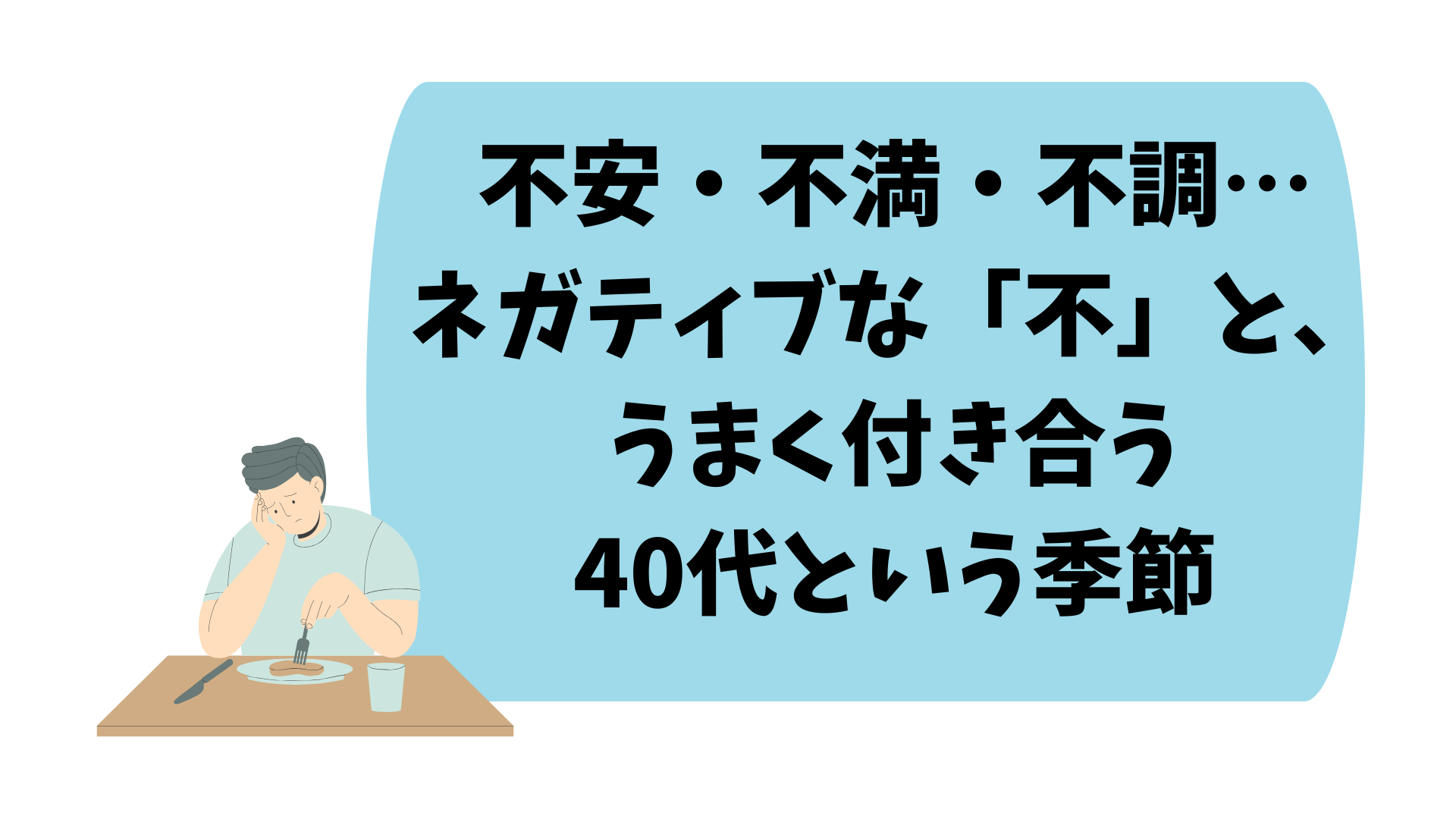
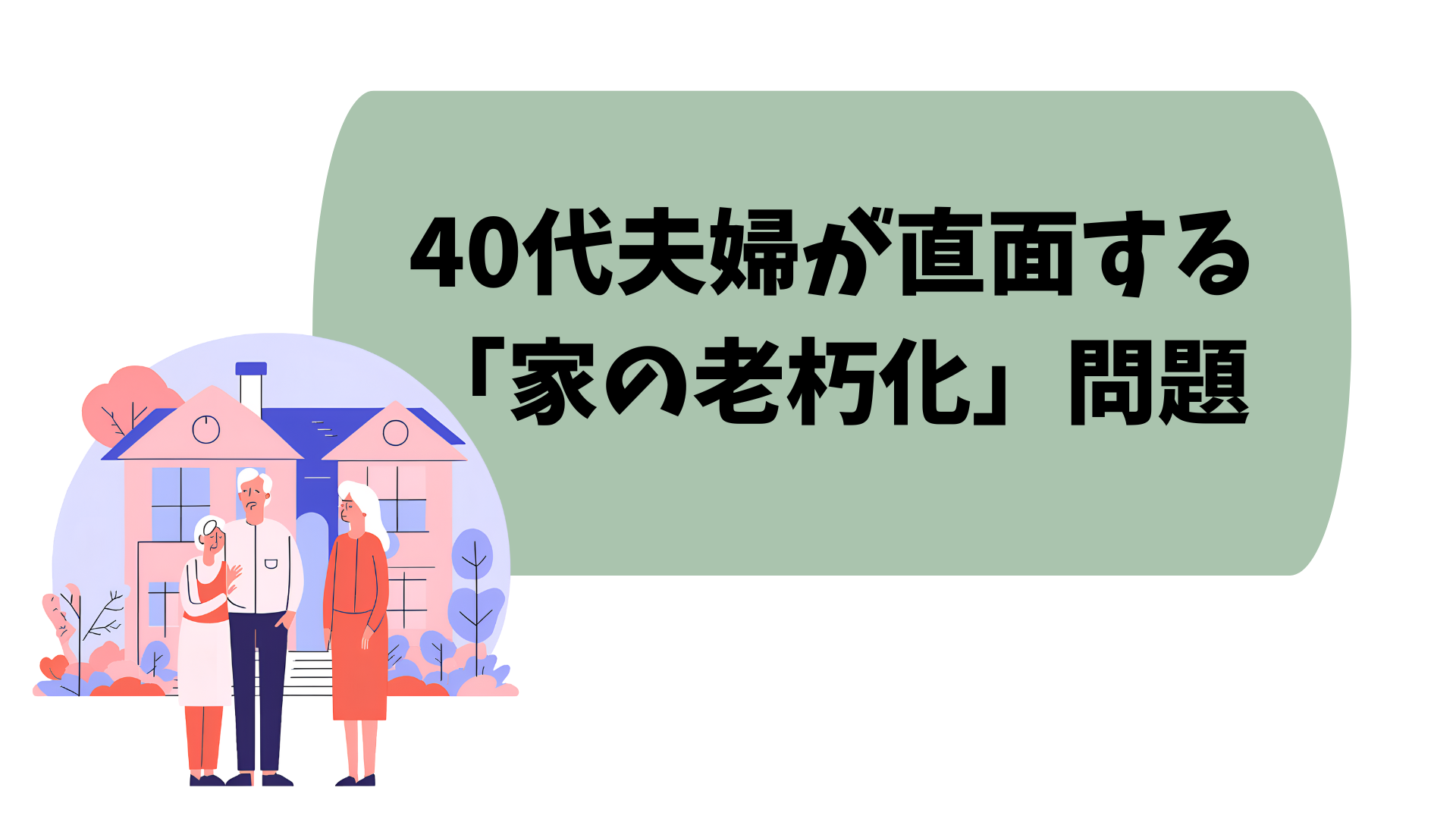
コメント